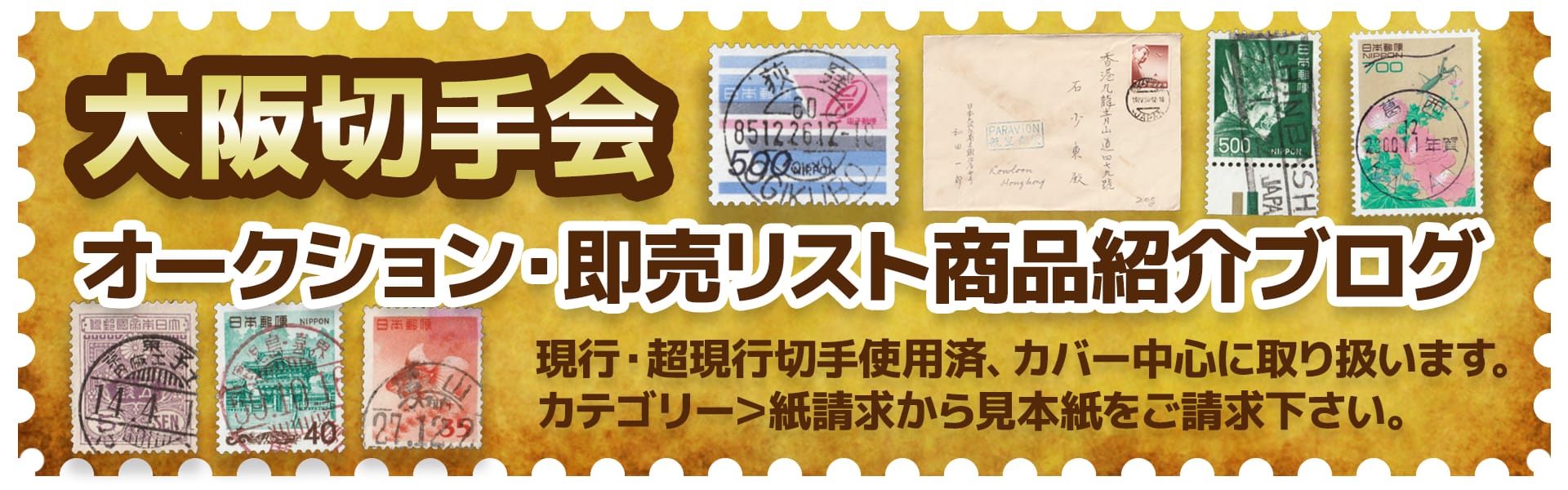大阪切手会オークション第46号連載記事紹介(2025.11.17)
読者様鉄郵投稿第7弾!!昭和58年九州収印記
ものすごいハードなスケジュール。九州南北横断や、新切手購入から僅かな時間での鉄郵印収印で大忙し。お目当ての収集品完成までの道のりをお楽しみください。(山本)
**************************************
昭和58年12月4日(日)晴。朝は冷え込んだものの天気は良好。佐世保駅前ホテルを出て、佐世保駅入場。9時46分、天草発、629D 普通列車 有田佐世保間下一便(キハユニ26)が到着。

↑佐世保駅に到着した、キハユニ26(有田佐世保間下一)。午後、折返し上二となる。

↑キハユニの乗客が降車後、回送で発車直前の様子。郵便室にも入室可能。車両中ほど1/4の狭いスペースで、乗務員は2名が基本
列車は回送となる為、車内外の写真撮影だけ行う。暫く、佐世保駅、佐世保分局等でリサーチをし、お昼は諫早駅へ行き、最後の島原鉄道の郵便車の現況を確認(本紙41号島原鉄道訪問記参照)し、午後、予定通り熊本、鹿児島方面に向かう。
鉄郵印が、来月1月末で全廃となる為、昨日土曜日から2泊3日で、久々九州へ来ているが、師走は仕事多忙で、有休は12/5(月)1日のみ。九州鉄郵収印は最後になりそうで、観光はカットし、鉄郵に専念する。

↑佐世保分局で到着便の押印依頼。この便は本日は既に終了という事で翌日付で押印、配達
夕方、熊本駅で途中下車し、駅構内の熊本鉄道郵便局熊本駅郵便室に立ち寄る。到着した便や駐在印等、保管庫にある日付印を押印依頼。続いて次の特急に乗り、西鹿児島駅(現・鹿児島中央駅)に到着した時はすでに20時台で、今晩は駅南のホテルに宿泊。
鹿児島での今回の目的の一つは、明日12/5発行の人権宣言35年記念切手の幻の前日印FDC作成。門司鹿児島間西回下三便、及び東回下二便は、午前9時台に終着の為、前日印FDC差出しは物理的に不可能。しかし、先日の高松での到着便の成功事例もあり、最後ゆえ、鹿児島でも終着駅での実逓FDC(速達等)差出依頼にトライしようと思う。
12/5(月)晴。8時半過ぎにホテルを出発、西鹿児島駅前の鹿児島中央郵便局に入り、本日発売の記念切手を確保。FDCに切手貼付後駅に入場。
まず、鹿児島本線ホームには、9時24分、急行荷物列車2037 門司鹿児島間西回下三(熊鹿)便が到着。郵便車両は、全車郵便車「オユ11」。到着便(終着駅)ゆえ、郵便物の差出はできないが、関西から最後の記念に収印に来た事情を話すると、快くFDCを受け取っていただき、押印して送付するとの事。

 ↑前日印FDC。門司鹿児島間東回下ニ(宮鹿)西鹿児島駅ホームで記念押印し、中央局で絵ハト印で差出分&前日印FDCの印影部分。門司鹿児島間西回下三(熊鹿)便。西鹿児島駅到着時、ホームで熊本鉄郵乗務員に発送依頼したもの。
↑前日印FDC。門司鹿児島間東回下ニ(宮鹿)西鹿児島駅ホームで記念押印し、中央局で絵ハト印で差出分&前日印FDCの印影部分。門司鹿児島間西回下三(熊鹿)便。西鹿児島駅到着時、ホームで熊本鉄郵乗務員に発送依頼したもの。
なお、九州では昭和50年より、東京門司線から直通の門鹿西回線のみ(門司熊本間も含む)、
東門線特例同様、速達のみの取扱となっている。
続いて日豊線ホームには、9時43分 2523 客車普通列車 門司鹿児島間東回下二(宮鹿)便 が到着。最後尾はこちらも全車郵便車「オユ11」。本便も前日印で、到着便で差出はできないが、FDCのペア貼りの切手片方にその場で記念押印をいただけた。熊本鉄道郵便局の方々は、大阪駅と異なり、皆様非常に親切。
そのあと、改札を出て再び、鹿児島中央郵便局の窓口を訪問、先ほどのFDCのペア貼りの門鹿東回前日印押印済のもう片方の切手に絵ハト印を押印し、発送依頼する。
これで、本日の主目的の「幻の前日印実逓FDC」 2便分は、無事発送終了。適正便とは言えないが、個人的には鉄郵最後の記念品にしたい。
続いて同じ局舎内の熊本鉄郵局鹿児島分局を訪問、所掌便全便分のFDCの押印依頼をし、これらは預けて帰る。
帰路は、鹿児島空港から大阪空港への空路が近道であるが、最後の機会でもあり、再び、鹿児島本線を博多駅まで逆戻りし、途中駅でFDCを作成をしながら、小刻みに移動した。1日で数十便の大量のFDCが作成できたが、帰宅は深夜になってしまった。




↑帰路に収印した各便抹消印&未納不足印
今回は要所要所で未納不足、抹消印も依頼。熊本鉄郵局の未納不足印は手数料表示の有無、
局名表示短縮型のもの等バラエティが多い。不足手数料表示があるタイプは、全て手数料
20円時代の「20」の部分のゴム印削りで、「30」
を手書きして使用し、新規作成はしていない模様。
抹消印は大小、字体違いあり、こちらも多少
バラエティがある。
なお、昭和50年台の鉄郵末期、門鹿西回、東回に、D欄「廻」の字体の使用例の報告があるようだが、私のほうでは、実際、郵便車内での使用例は確認できていない。本局へ押印依頼の予備印のCTOではないかと推測されるが、今となっては定かではない。(完)
大阪切手会オークション第45号連載記事紹介(2025.5.18)
毎回好評読者様投稿第6弾!!
大阪駅等 普通切手FDC作成日記
昭和55年10月1日(水)曇時々晴。10月にしては少し蒸し暑い。本日は、ちょうど休みで、タイミングよく、久々の新図案普通切手の発行日で、額面は30円40円50円の3種類。
朝、自宅最寄りの郵便局で必要数確保し、国鉄大阪駅へ向かう。
本日最初は、大阪駅10時17分発 東京門司間上五浜阪(急行荷物列車2032)便、続き10時31分発 東京門司間下四阪糸(急荷39列車)便。大阪駅に到着時は両便ともホームで出発待ち。郵便車両は両方共、全車郵便車「オユ11」で、荷物列車12両編成中、中ほどに連結。両列車とも始発駅を昨晩出発の為、前日印となる。
この東門線は、昭和47年施行の取扱特例により、輸送合理化の為、速達のみの引受となり、FDCは全て速達にする必要あり。
 ↑東門上五浜阪・下四阪糸・下五阪糸 前日印。(大阪駅にて差出)大阪鉄郵(阪糸)は、これでも当時は、かなり美印のほう。(私見)
↑東門上五浜阪・下四阪糸・下五阪糸 前日印。(大阪駅にて差出)大阪鉄郵(阪糸)は、これでも当時は、かなり美印のほう。(私見)
2便差出後、すぐ京都駅へ向かう。京都駅 11時53分発、東京門司間下五浜阪(急荷2031列車)便に差出し、トンボ帰りで大阪駅に戻る。
 ↑東門下五浜阪前日印FDC。(京都駅にて差出)本日、唯一、宛先と列車の行先が合致する適正便。
↑東門下五浜阪前日印FDC。(京都駅にて差出)本日、唯一、宛先と列車の行先が合致する適正便。
まもなく先ほどの郵便列車が到着。こちらの車両も「オユ11」。大阪駅で、名古屋鉄道郵便局から大阪鉄道郵便局に乗務員が交代する(浜阪→阪糸)が、この便もギリギリ昨晩出発の為、日付は引き続き前日印が使用される(注 : 翌昭和56年6月、規則改正で、乗務員交代時に、日付はその交代日の日付を使用するというルールに変更される)。
 ↑国鉄大阪駅 3番線に停車中の「オユ11 1007」(東門下五)。大阪駅では、日常普通に見かける光景であった。
↑国鉄大阪駅 3番線に停車中の「オユ11 1007」(東門下五)。大阪駅では、日常普通に見かける光景であった。
本日はこれで前日印 4便終了。続いて、10番線北陸線ホームには、13時31分発 大阪金沢間下阪敦(荷1048列車)便が、短い3両編成で入線。最後尾は、こちらは全車郵便車両「オユ10」。この便は速達ではなく、普通郵便でOKだが、宛名書は必須。 ↑阪金下阪敦、阪鶴下、阪福下二。(大阪駅にて差出)
↑阪金下阪敦、阪鶴下、阪福下二。(大阪駅にて差出)
 ↑大阪駅 2番線に停車中の「スユニ50 2003」(阪鶴下)。手前側半分が郵便室。福知山線では普通列車にも郵便荷物車両は、よく連結されていた。
↑大阪駅 2番線に停車中の「スユニ50 2003」(阪鶴下)。手前側半分が郵便室。福知山線では普通列車にも郵便荷物車両は、よく連結されていた。
少し時間があき、次は2番線福知山線ホームに15時07分発、大阪東舞鶴間下(福知山行 737普通列車)便が入線。福知山線は、全線電化でないため、ディーゼル機関車が客車を牽引、先頭から2両目が郵便荷物車両 スユニ50で、3両目以降は客車の編成。大阪駅発着の郵便車の中では、阪鶴線は唯一、半車郵便車両となる。
本日は、未納不足印、抹消印も適宜依頼。大阪鉄郵局の未納不足印は、書体、大小にバラエティが多く、現在、旧字体「圓」や、「乗務員」の文字入りもあり、また分局名入の印もあり、他局に類を見ない。
抹消印は概ね同じ形式であるが、大小、字体にバラエティがある。


↑車内で使用の、大阪鉄郵局の未納不足印、抹消印。
なお、大阪駅では、大量の郵袋の受渡しがあり、幹線の郵便車内は、郵袋が天井まで積上がる事もあり、多忙で、記念押印などは不可。宛名を書いた郵便物も、列車の行先と宛先が異なる(通称 逆送)と、受取り拒否される事も多い。
従って、ホームで郵便車へ収集家からの差出依頼は、車中業務に支障があり、原則引受けず、日付印は大阪鉄本局計画課へ押印依頼するよう、乗務員には通達が出されている。ホームでは少数通なら受けてもらえるが、美印が少ないのが悩みのタネ。昭和50年台の車中印の美消は希少で、大阪鉄は収印に苦労が多い。

参考までに、同時期の本局計画課で使用の予備印も末尾に一部掲載しておく。活字の摩耗がなく、初日ハト印のようにリングが綺麗、また、印刷のような仕上がりが特徴で、車中の印とは明確に判別ができる。(完)
大阪切手会オークション第44号連載記事紹介(2024.10.24)
鉄郵訪問収印記第5弾!今回は高松坂出(香川県)収印記です。
青春18きっぷ利用で鉄郵印収印、郵便車両の見学や撮影を楽しむ企画。
ヘッドマーク掲出の郵便気動車が面白い。お楽しみ頂けると幸いです。
******************************
高松坂出(香川県)鉄郵印収印記
今回は夏休みを利用し、「青春18きっぷ」の綴り4枚目の2日間有効券を利用して、1泊2日で、久々、高松まで足を延ばすことにする。
昭和58年8月14日(日) 快晴。朝、兵庫県の自宅を出発し、国鉄東海道・山陽本線、岡山駅から宇野線に乗り継ぎ、宇野駅下車後は宇野港から、宇高連絡船 (国鉄船で、青春18 利用可。昭和63年 瀬戸大橋開業に伴い運航終了) に乗り、16時頃、高松駅に到着。
途中、岡山駅では、岡山玉野間下ニ護送便(広島鉄郵局所掌)に出会い、記念押印だけ依頼。この列車は、東京・汐留発の荷物専用列車で、岡山までは東京岡山間下護送便、岡山から分かれて宇野駅(玉野局)まで、別の荷物列車で、宇野港から郵便車も航送(無人の締切便)、高松駅到着後、上便で東京に戻る。(東京 ↔ 四国の直通便)

↑岡山玉野間下ニ護送印。(岡山駅にて。広島鉄郵局所掌)
今日は、今年一番の猛暑で非冷房の郵便車の乗務員の方々も悲鳴の暑さ。夕方、予定を早めに切り上げ、夕食に高松駅構内の料理店で、鰻とビールを注文、ひと息ついてから、予讃線で高松駅から30分ほどの坂出駅のホテルに向かう。
翌朝、8月15日(月)は、洋風建築シリーズ第9集の発売日で、主な目的は前日印FDCの作成。
今から2年少し前の昭和56年6月、予告なく突然、規則改正で、鉄郵前日印が大半姿を消した。以前は列車の始発日の日付が終着駅まで変更されなかったが、改正後は乗務員交代時(C欄変更時)に日付も変更される。しかし、まだ全国でわずかに長距離路線で前日印可能便が残り、この四国の予讃線の便もそれになる。
朝、坂出駅前ホテルを出発、坂出駅には、8時47分発、高松行 202D 急行土佐 1 号が到着。5両編成最後部には、郵便荷物車両「キユニ26-17」が連結されている。この便は、高松中村間上ニ(前日印)であるが、残念ながら郵便局開局時間前で、手元に記念切手はなく、車両を眺めるだけとなる。


上:坂出駅に停車中の急行土佐号の最後尾「キユニ26 - 17」(高松中村間上ニ)
下: 一緒に高松駅まで乗って来た普通列車の最後尾「キユ25 - 2」(高松宇和島間上ニ)
そのあと、最寄りの郵便局で記念切手を購入し、再度、坂出駅入場。9時50分頃、今度は高松行 138D 普通列車が到着。5両編成最後部には、四国固有の全車気動車郵便車「キユ25 - 2」が連結、この便は、高松宇和島間上ニ(前日印)であり、積載郵袋数も相当多く、唯一冷房車。終着高松駅までは時間もわずかで、FDC差出は迷惑と思い、記念押印だけ依頼。「押したら座席にお届けします!」と仰せで、急いで隣接車両の郵便室に近い座席に座り込む。ほどなく高松鉄郵乗務員の方が、押印済FDCを持って、冷房の効いた郵便室から出てこられ、御礼を言って受け取る。郵便車と共にローカル線前日印FDC作成の旅、実にリッチな気分だ。

↑高松宇和島間上ニの前日印FDC(坂出駅で依頼分)。高松局で特印押印し、差立
10時15分 高松駅到着後、すぐに駅構内の高松鉄郵局高松駅郵便室を訪問。先ほど 9時過ぎに既に到着便の高松中村間上ニの押印について、ダメもとで依頼してみると、「いいですよ!」と快く応諾くださり、保管庫から日付印箱を出してくださり、前日印を押印いただけた。高松鉄郵の方々は、皆様いたって親切。しかし、これ以上調子に乗ってもよくないと思い、早々に退散する。

↑高松中村間上ニ前日印FDC抜粋。(高松駅郵便室にて押印依頼分)
続いて、高松郵便局訪問。ペアの記念切手の片方の切手に絵ハト印を押印し、それを引受消印として発送する。目的の前日印FDC2便の実逓便作成は完了。
次に同局舎内の高松鉄郵局本局も訪問、本日のFDCに高松鉄所掌便全16便の押印依頼、これは預けて帰る。この高松鉄郵局の予備印の印影も最後に掲載しておく。予備印は車内で使用の日付印と活字は酷似するが、リングが綺麗な為、何とか判別は可能である。そのあと、高松駅でしばらく郵便車の写真撮影を始め、未納不足印、抹消印も、都度依頼したが、同局分はバラエティはなく、全て同じ形状であった。午後、高松を出発し帰路につくが、岡山駅でも途中下車をし、広島鉄郵局岡山分局を訪問する等、結局、鈍行列車の旅ゆえ、帰宅は深夜になった。



上中段:高松鉄郵本局で使用の予備印(8/15付の印 2枚。記念押印に前日印は押印しない) 下段:高松鉄郵局未納不足印、抹消印
大阪切手会オークション第43号連載記事紹介(2024.5.20)
本紙の皆様への発送は5月23日頃の予定です。
皆様からご好評頂いている鉄郵訪問収印記第4弾です。今回は播州地方の国鉄消収印記。
記念切手発行初日印を追い求める、まさに鉄郵版局巡り。時刻表を繰りながらいろいろ考えて効率良い予定を立て、狙い通りクリアできたときの充実感は最高でしょう。ユニークな気動車鉄郵車両写真と併せ、お楽しみ頂けると幸いです。
************************************
播州地方 鉄郵印収印記
*これは、昭和55年、大学時代の夏休みに、播州地方を訪問した時の日記です。
鉄郵印は、ふだんは兵庫県の自宅から1時間ほどの大阪駅で、郵便列車の乗務員に直接手渡しをして依頼しているが(記念押印は不可)、本日は夏休みを利用し、この9月末で廃止予定の、播州地方(兵庫県南西部)の珍しいローカル線の郵便列車を訪ねる事にする。
↓路線図。現在は廃線となっている分岐線(鍛冶屋線)も

7月23日(水) 薄曇り。本日は「ふみの日の切手」発売日でもあり、FDC作成も行う。午前中の便がない為、本日最初は、昼すぎの加古川線の加古川西脇間上便となる。この便は、早朝、普通列車に併結されて加古川駅を出発、野村駅(現・西脇市駅。西脇局受渡)より、支線・鍛冶屋線(1990年廃線。営業キロ数13.2km)に入り、終着・鍛冶屋駅(松井庄局受渡)で折り返し上り便となり、昼すぎに加古川駅に戻って来る短い路線である。日付印は、加古川西脇間下、西脇松井庄間下、西脇松井庄間上、加古川西脇間上と同じ日付印軸で、午前中 4回、活字が更植される。
自宅から約2時間半、お昼頃、のどかな加古川線厄神駅(加古川駅より3駅目)に到着。まもなく受渡局・国包郵便局員が郵袋を持って、ホーム先頭あたりに入場、3両編成の上り744D普通列車が到着。先頭が郵便荷物客室合造車・キハユニ15-6、車両の色はピンク1色塗装(首都圏色)。この車両は全国的にも珍しく、加古川気動車区には、あと、キハユニ15-3、15-9型の合計3両の珍車両が在籍。(あとの2両は2色塗装。)


上:一緒に乗り、加古川駅に到着した「加古川西脇間上便」の「キハユニ15-6」。到着後、混雑が収まった頃。赤い台車には、大鉄局加古川駅の文字が見える。
下:姫路駅姫新線ホームで出発を待つ、姫路広島間下ニ(姫新)便。「キユニ18-7」が先頭。(米子鉄道郵便局所掌便)
車両の中ほど1/4の狭い郵便室内には大阪鉄道郵便局姫路分局乗務員3名が乗務。うち、1名は押印台で、何処で差出されたか?ふみの日切手FDCらしいカバーを猛スピードで押印していた。急いで私の分の郵便物を手渡し、同じ車両の客室に乗り込む。隣の郵便室との間の扉は施錠されてないが、当然立入りは禁止。
15分ほどで終着・加古川駅に、13:09到着。そのあとの行動は忙しく、加古川駅から、姫路駅(約20分)へ向かい、ホームで名物駅そばを食べたあと、播但線ホームで出発待ちの姫路和田山間下二(キユニ26-7。和田山行普通列車)へFDCを差出し、再び加古川駅へ戻る。
次の加古川線の14:57発 谷川行 743D普通列車には、加古川谷川間下便が連結され、14時半過ぎに入線。車両は先ほどと同じで、乗務員は別チームであるが、日付印箱は先ほどの加古川西脇間上と同じものを携帯するらしく、A欄C欄を更植するだけで、活字のバラエティはない。
この頃、姫路駅では、東京門司間下五便(こちらは前日印)の発着があるが、差し出すタイミングが合わず。
加谷下便を見送ったあと、再び、姫路駅へ戻るが、播州地方は激しい雷雨となる。
小雨になった頃、姫新線の16:58発 津山行 843D普通列車に連結の姫路広島間下二便(キユニ18-7。所掌は米子鉄郵局で、車両は岡山気動車区所属)を差出し、本日は終わりにする。
この便は9/30で、姫路広島間の東半分の姫路新見間(米子鉄郵、姫新線部分)が鉄道郵便輸送が廃止されるが、西半分の新見広島間(広島鉄郵所掌。芸備線部分)は存続する。当然、姫路広島間という日付印はなくなり、10/1からは、新見広島間という日付印が新設されるが、これも鉄郵の面白いところである。
加古川気動車区は珍郵便荷物車両で注目されていたが、昭和55年10月1日のダイヤ改正で全て廃車となり、鉄郵印も多数廃止された。9月末、上記の便以外に大阪鉄郵局姫路分局所掌の西舞鶴豊岡間4便(宮津線)も含め、兵庫県内発着のローカル線だけでも、18印の鉄郵印が姿を消した。
加古川線の日付印は、20年以上継続使用と思われ、摩耗がはげしく、印影の通り、美印は難しい。参考までに、同時期に大阪鉄道郵便局本局に郵頼した記念押印日付印の印影も掲載しておく。現在、残っている当該便の満月印やエンタイアは、ほとんどが、この予備印で、活字体やリングの摩耗度で明確に判別できる。


上:作成したFDC(抜粋)。下:50円コイル切手は、大阪鉄道郵便局本局へ別途、郵頼した記念押印(予備印)。