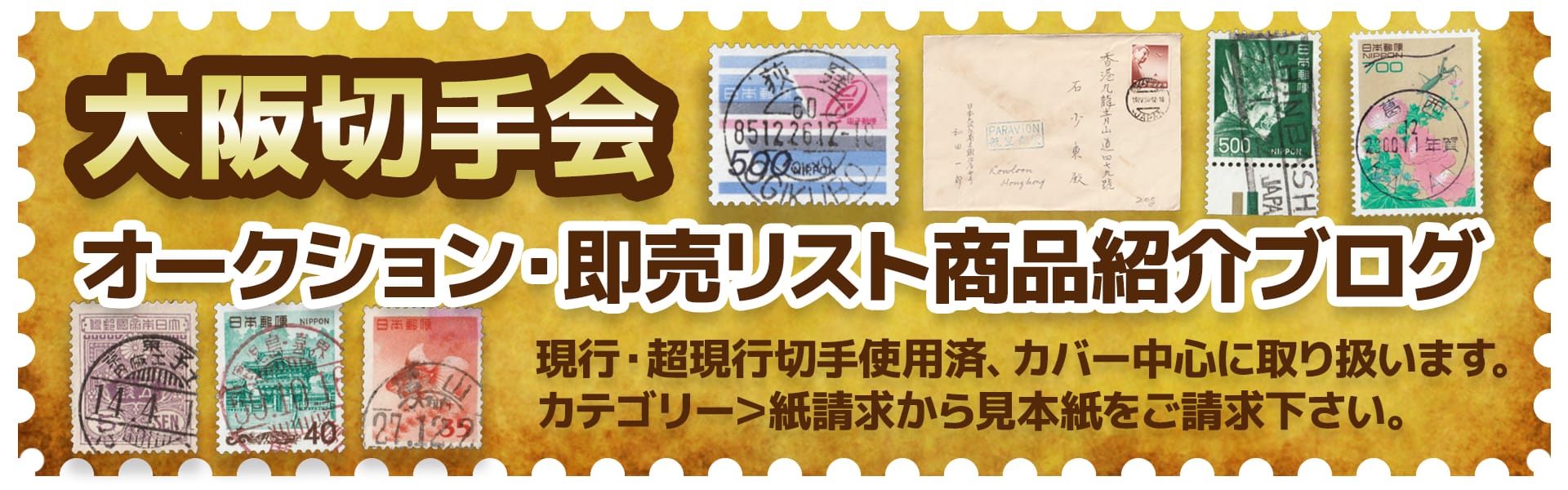毎回好評読者様投稿第6弾!!
大阪駅等 普通切手FDC作成日記
昭和55年10月1日(水)曇時々晴。10月にしては少し蒸し暑い。本日は、ちょうど休みで、タイミングよく、久々の新図案普通切手の発行日で、額面は30円40円50円の3種類。
朝、自宅最寄りの郵便局で必要数確保し、国鉄大阪駅へ向かう。
本日最初は、大阪駅10時17分発 東京門司間上五浜阪(急行荷物列車2032)便、続き10時31分発 東京門司間下四阪糸(急荷39列車)便。大阪駅に到着時は両便ともホームで出発待ち。郵便車両は両方共、全車郵便車「オユ11」で、荷物列車12両編成中、中ほどに連結。両列車とも始発駅を昨晩出発の為、前日印となる。
この東門線は、昭和47年施行の取扱特例により、輸送合理化の為、速達のみの引受となり、FDCは全て速達にする必要あり。
 ↑東門上五浜阪・下四阪糸・下五阪糸 前日印。(大阪駅にて差出)大阪鉄郵(阪糸)は、これでも当時は、かなり美印のほう。(私見)
↑東門上五浜阪・下四阪糸・下五阪糸 前日印。(大阪駅にて差出)大阪鉄郵(阪糸)は、これでも当時は、かなり美印のほう。(私見)
2便差出後、すぐ京都駅へ向かう。京都駅 11時53分発、東京門司間下五浜阪(急荷2031列車)便に差出し、トンボ帰りで大阪駅に戻る。
 ↑東門下五浜阪前日印FDC。(京都駅にて差出)本日、唯一、宛先と列車の行先が合致する適正便。
↑東門下五浜阪前日印FDC。(京都駅にて差出)本日、唯一、宛先と列車の行先が合致する適正便。
まもなく先ほどの郵便列車が到着。こちらの車両も「オユ11」。大阪駅で、名古屋鉄道郵便局から大阪鉄道郵便局に乗務員が交代する(浜阪→阪糸)が、この便もギリギリ昨晩出発の為、日付は引き続き前日印が使用される(注 : 翌昭和56年6月、規則改正で、乗務員交代時に、日付はその交代日の日付を使用するというルールに変更される)。
 ↑国鉄大阪駅 3番線に停車中の「オユ11 1007」(東門下五)。大阪駅では、日常普通に見かける光景であった。
↑国鉄大阪駅 3番線に停車中の「オユ11 1007」(東門下五)。大阪駅では、日常普通に見かける光景であった。
本日はこれで前日印 4便終了。続いて、10番線北陸線ホームには、13時31分発 大阪金沢間下阪敦(荷1048列車)便が、短い3両編成で入線。最後尾は、こちらは全車郵便車両「オユ10」。この便は速達ではなく、普通郵便でOKだが、宛名書は必須。 ↑阪金下阪敦、阪鶴下、阪福下二。(大阪駅にて差出)
↑阪金下阪敦、阪鶴下、阪福下二。(大阪駅にて差出)
 ↑大阪駅 2番線に停車中の「スユニ50 2003」(阪鶴下)。手前側半分が郵便室。福知山線では普通列車にも郵便荷物車両は、よく連結されていた。
↑大阪駅 2番線に停車中の「スユニ50 2003」(阪鶴下)。手前側半分が郵便室。福知山線では普通列車にも郵便荷物車両は、よく連結されていた。
少し時間があき、次は2番線福知山線ホームに15時07分発、大阪東舞鶴間下(福知山行 737普通列車)便が入線。福知山線は、全線電化でないため、ディーゼル機関車が客車を牽引、先頭から2両目が郵便荷物車両 スユニ50で、3両目以降は客車の編成。大阪駅発着の郵便車の中では、阪鶴線は唯一、半車郵便車両となる。
本日は、未納不足印、抹消印も適宜依頼。大阪鉄郵局の未納不足印は、書体、大小にバラエティが多く、現在、旧字体「圓」や、「乗務員」の文字入りもあり、また分局名入の印もあり、他局に類を見ない。
抹消印は概ね同じ形式であるが、大小、字体にバラエティがある。


↑車内で使用の、大阪鉄郵局の未納不足印、抹消印。
なお、大阪駅では、大量の郵袋の受渡しがあり、幹線の郵便車内は、郵袋が天井まで積上がる事もあり、多忙で、記念押印などは不可。宛名を書いた郵便物も、列車の行先と宛先が異なる(通称 逆送)と、受取り拒否される事も多い。
従って、ホームで郵便車へ収集家からの差出依頼は、車中業務に支障があり、原則引受けず、日付印は大阪鉄本局計画課へ押印依頼するよう、乗務員には通達が出されている。ホームでは少数通なら受けてもらえるが、美印が少ないのが悩みのタネ。昭和50年台の車中印の美消は希少で、大阪鉄は収印に苦労が多い。

参考までに、同時期の本局計画課で使用の予備印も末尾に一部掲載しておく。活字の摩耗がなく、初日ハト印のようにリングが綺麗、また、印刷のような仕上がりが特徴で、車中の印とは明確に判別ができる。(完)